17.望月
「今日は満月か」
シリルのぼやく声に、店内清掃に使うアルコールを補充していた僕は手を止めて、携帯端末で月齢カレンダーを表示させた。確かに、彼の言葉どおり今夜は満月だった。しかも珍しく晴れる予報になっている。
そのことにシリルが酷いしかめ面をしていた。しかめ面をしながら手早くパイ生地を編み込んでいる。
「満月だと、何かあるの?」
「どうだろうな。何もない方がいい」
要領を得ない言葉だ。何かをはぐらかされてる感じ。「どういう意味?」「なんでもねーよ」自分から話を振ってきたくせに、これ以上話すことはないとばかりにシリルは今日の夜ご飯だというパイ作りに意識を向けて、僕を放り出してしまった。
なんでも、パイ生地作りに失敗した部分で、客には出せない生地だから食べてしまいたいんだとか。それで、今晩は適当におかずや残り物を詰めたパイが夜ご飯、というわけだ。今は空き時間でその仕込みをしている。
……それにしたって、満月がなんだっていうのか。
パイ作りに集中したいだろうシリルを邪魔する気は起きなくて、アルコールのボトルの中身を補充してからお客さんが来ていない店舗の方に戻ると、リリーが手持ち無沙汰だという感じで店内を歩いていた。埃を見つけると手にしたタオルで拭い、汚れはないかと目を凝らしている。
「リリー」
「、はい」
「今日は雨だから、客足は遠のくよ。ちょっと休憩しよう」
僕がコーヒー豆の入った袋を揺らすと、リリーはどこかほっとしたように一つ頷いた。
そう、今日は雨だ。
ポツポツというよりはポタポタという、濡れるのは嫌だなと思う粒が大きめの雨が朝から降り続いている。
それなのに、今夜は晴れて満月が見えるのだそうだ。このあと晴れてくるのだろうか。
三人分のコーヒーを淹れて、シリルのはキッチンのテーブルに置いて、リリーと二人で熱いコーヒーをすすった。
キッチンからはオーヴンが予熱される駆動音がしている。
目の前にはイギリス人らしいブロンドヘアの女の子がいて、僕の淹れたコーヒーを飲んでいる。
これが、今の僕の日常だ。
行く場所がないというリリーのことを追い出せず、シリルに睨まれたり呆れられたりしながら、僕は、この三人での生活を良いものだと思い始めている。
(こんな何気ない時間が、なるべく長く続けば。この店がこのまま軌道に乗れば。シリルに頼らず、貯金も崩さず、運営できるようになれば。そうしたら……)
そうしたら。リリーのことだってちゃんと受け入れてあげられて。そうしたら、僕は、少し、自分に自信が持てそうなのにな。

その日の夕方、強くて寒い嵐のような風が吹き荒れ雨雲をさらい、そのまま夜が訪れた。
ガタガタと揺れていた窓が静かになったと思って外を覗いたら、路面は雨粒に濡れていたけれど、暗い空には星が瞬いていた。
(驚いた。本当に晴れた)
グズグズとした天気が続くことが多い英国では珍しく雲一つない夜空だ。
思わず窓を開けると、冷たい風が吹き込んできた。バサバサと祖父の机の上の紙の束や積んだままの本のページが揺れる。「さみぃだろうが」タブレットのディスプレイを睨みながらシリルが棘のある声を出す。それにごめんと謝って、それでも窓から顔を出して空を見上げ続ける。
満月だ。月が丸い。なんだか、彼女みたいな色をしている。
その彼女は、枕元で丸くなって眠っている。
事情を知らないリリーには彼女のことは『食物摂取でエネルギーを得られる最新式のドラゴン型AIだ』ということにしているから、彼女のサイズはあれから少しも変わっていない。そういうふうにしてくれているのだと思う。
寒いなぁと腕をさすりながらも満月から目を離せずに空を見続けていると、ふと、通りで動くものがあった気がしてそちらに目がいった。
(リリー?)
窓から身を乗り出して「リリー?」と声をかける。届かないのか、気付いていないのか、彼女は茶色いコート姿で歩いて行ってしまった。
神妙な顔のシリルが隣にやってきて、満月の空と、リリーが消えていった方角を見やる。
「何も起きないとよかったんだがな」
「昼間も言ってた。それ、どういう意味?」
「満月は月の引力が強くなる。血圧も高くなって犯罪が増える傾向にある、と科学的にも立証されてる」
「…それが、何?」
「魔術の世界でも、満月は魔力が強くなる傾向にある」
魔術。魔力。
シリルは馴染みのない言葉をスラスラと唱えていく。当たり前のように。「ここまで何もなかったが、リリーには怪しい点があった」「え?」「お前はこっち側を知らないから気付かなかっただけだ。実際、そこのドラゴンも、リリーからは取れない血の臭いがするって言ってたぜ」顎でしゃくって眠り続ける金のドラゴンを示されて、僕は言葉をなくしてしまった。
ささやかなしあわせの日常が、三人の朝が、テーブルを囲んでの食事が、コーヒーの時間が、砂の城のように呆気なく崩れていく……。
ぎゅっと拳を握って、解く。
リリー。やわらかなブロンドヘアをした、素直な女の子。嘘のつけない女の子。
僕は彼女が僕らを騙していたとは思えない。…思えないんだ。それは僕が馬鹿でお人好しだからかもしれない。
(だけど。それでも。そうだったとしても)
スウェットパジャマの上からコートを羽織って部屋を飛び出し、シリルの制止も聞かず、街灯の少ない町でリリーの茶色のコートを探した。見つからない。スーパーの前にも、教会にも、最初に会った駅にも、彼女の姿はない。
駅を出たところで上下ジャージ姿でコートを羽織ったシリルが僕に合流し、あちこち駆けずり回って疲れている僕を見て呆れたように口をひん曲げた。「そんなに連れ戻したいのか」と言われて、なんと返すべきか、と言葉に迷う。
事情を知らない赤の他人を、くたくたになるまで駆けずり回って探して、それがどうしてかって訊かれたら………連れ戻したいのかと、訊かれたら。僕は、イエスと、言うのだろうか。
「………わからない。わからないけど、わからないから、探してる」
僕が捻り出した答えに、シリルは肩を竦めた。「たぶんこっちだ。ついてこい」と言われ、大股で歩き出した彼を小走りに追いかけると……町の外れ。山の麓。山の影に呑まれて星の光も届かない暗闇に、ポツンと一つだけ街灯があって、その下にリリーの茶色いコート姿があった。
頭上には、まん丸の月。
その金の円はなんだか異様に大きく見える。
「リリー」
やっと見つけた、とホッとしたのも束の間のこと。
俯けていた顔を持ち上げてこっちを見たリリーの目は赤かった。…見間違いではない。何度瞬きをしても同じだ。リリーの目はルビーのように赤い。
人の目が赤いとか、尋常じゃない。
その赤に見据えられて思わず足を止めた僕に、これ以上近づくなとばかりにシリルが僕の前に腕を突き出す。
冷たい、とても冷たい風が吹き荒れて、体温を奪っていく。
寒い。風のせいだけじゃない。この一帯の空気が異様に冷たい。
「ノア・ステュアート・オブ・ダーンリー」
リリーの声に温度はなく、感情もなく、ただただ無機質な、まるで機械のような抑揚で僕の名前を読み上げた。
彼女が自分の指を噛む。その指から血が滴って地面に落ちる。その地面から、むくむくと、何かが膨らんでいく。「……、」何かが。手足が八本あって、今にも崩れそうなグズグズとしたダンゴムシのような体に、顔が。眼球が落ちくぼんだ人の顔が…。
血でできた真っ赤なソレは、人の顔で、僕を見ていた。「…っ、」思わず一歩下がってしまう。
僕の知らない世界。僕の知らないモノ。僕が知らない、リリー。
「わたしには、金の竜が必要です」
「え…?」
「アレを差し出してください。そうすれば、あなたの命は助かる」
金の竜。彼女が必要? 確か、そんなことをあのときのシリルも言っていた。僕に銃を向けたシリル。それで撃たれたりしたっけ。
思わずそのシリルを見やる。彼は口をひん曲げていた。気に入らない、という顔でリリーのことを見ている。僕のように未知の存在に思考を停止させているわけではなく、この現実を受け止めて、気に入らない、という顔をしている。
そう。これは彼が言っていた『こっち側』で、僕から言えば『向こう側』の世界なのだ。
「お前、あのクソジジイに何を言われたか知らないが、やめとけ。いいように使われてるだけだって気付いてるはずだろう」
リリーは何も言わずにまた指を噛んだ。滴る赤が、今度は彼女の手でナイフの形を取る。
シリルは肩を竦めて片手を掲げた。その手にリリーのと同じような一振りのナイフが握られる。 その切っ先が月光を受けて輝いたとき、その鋭さに、僕の思考がかろうじて動いた。「ま、待ってくれシリル。相手はリリーだ」応戦する気の彼をなんとか止めようとするが、返ってきたのは冷たい一瞥。
「ならお前、ドラゴンを差し出すのか」
「それは…、」
…できない。おじいちゃんの頃から喫茶店を見てきた彼女を、僕を孤独から救った彼女と、そんなお別れはしたくない。
シリルの左目が淡く光っている。彼女が与えた竜の目。
その向こうで、形容しがたい赤い何かがスルスルと動き出し、見た目よりもずっと速く動いて僕らに接近し…シリルのナイフの一薙ぎで弾け飛んだ。ナイフの刀身が月の光を受けて刺すように眩い。
「ジジイに聞いてないのか。オレは無力じゃない」
「…………」
ナイフを掲げたリリーは、自分の腕を切り裂いた。「リリーっ!」ぼたぼたと落ちる血の量に僕が悲鳴を上げてしまう。太い血管を傷つけでもしたら、失血死してしまうのに…!
落ちた血をリリーのコートが吸い上げ、真っ赤に染まったコートはまるで翼のように広がり、彼女は、飛んだ。まるで赤い翼をした有翼種のように。
リリーの血を吸い上げたコートから無数の赤いナイフが生えてきて、まっすぐに射出される。相対するシリルに向けて。ナイフの雨。シリルはそれを片手で防いだ。彼が掲げた左手には見えない壁でもあるのか、ナイフは彼の手前で弾けて消えていく。
「やめてくれ……」
無意識に、僕はそうこぼしていた。
リリーがまた自分の腕を傷つける。赤い血が落ちる。ナイフの形すら取らず、落ちた赤は弾丸のような速さで僕らの周囲を旋回し、逃げようのないすべての角度から僕らを貫く。
瞬きの間に、僕はシリルに引き寄せられていて、彼の背中から生えた真っ黒い翼に包まれていた。
彼が僕を守ったのだ、と理解するのに数秒かかる。
血の弾丸が止めば僕は下がってろとばかりに突き飛ばされて、シリルはそのまま、黒い翼で空に舞い上がっている。彼の視線の先にはリリーがいる。赤いナイフを構えたリリーが赤い翼を翻して飛ぶ。
「やめてくれ」
ナイフを交える二人の前で、僕はただ無力につぶやくことしかできない。
どうしてこんなことになってしまったんだ。どうして。どうして……。
17話め!
『満月』がトリガーでリリーの記憶が戻り、彼女は『ドール』として動き始めます
アリスの小説応援! にポチッとしてもらえると励みになります❤(ӦvӦ。)
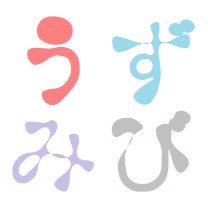






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません